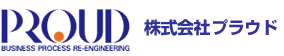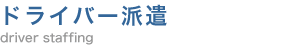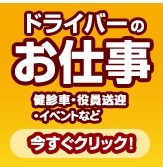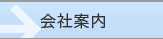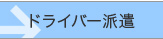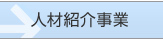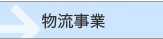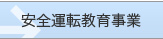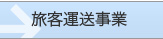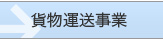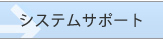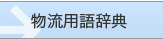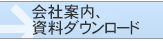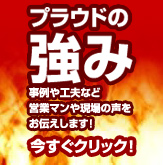派遣労働者の受け入れ期間
1.労働者派遣法改正により、変更された派遣受け入れ期間
2004年3月1日の労働者派遣法の改正により、これまで禁止された派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接、事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。変更点を下記の表でご確認ください。
| 業務の種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 有期プロジェクト業務 | プロジェクト期間内は制限なし | 変更なし |
| 日数限定業務 ※1 | 1年 | 制限がなくなりました |
| 製造業務 | 派遣禁止 | 1年 (平成9年3月から3年まで可能となります) |
| 産休産後、育児休暇の代替 | 2年 | 制限がなくなりました |
| 介護休暇を取得する労働者の業務 | 1年 | 制限がなくなりました |
| 45歳以上の中高年齢者の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年 | 変更なし |
| 自由化業務(上記以外の業務) | 1年 | 3年 ※2 |
※1
業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下で、10日以下の業務
※2
1年を超えて派遣を受け入れる場合、意見聴取が必要となります。詳しくは意見聴取を参照
2.派遣期間の算出について
派遣契約をした日を起点として期間を算出します。労働者派遣法改正前からの就業については、その派遣期間を通算されます。
3.意見聴取について
労働者派遣法の改正で1年から3年に延長されたことにより、事業主が職場の実状を的確に把握する事を目的とし、1年を超えて自由化業務の派遣労働者を受け入れようとする場合、派遣先労働者の過半数代表者などの意見を聞く事が義務づけられております。
また、意見聴取した内容は書面として記載し、3年間保存する事と定められています。
- 派遣労働者を受け入れる業務、開始時期および期間を定めます。
- 派遣先事業所の労働者の過半数代表者※1に対して、派遣を受け入れる業務、開始予定時期、期間を書面で通知します。
- 十分な考慮期間を設けた後に、派遣先事業所の労働者の過半数代表者から意見を聞く。
- 意見聴取した内容を書面※2に記載し、3年間保存する。
・当該労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
・通知した日、および通知した事項
・意見を聞いた日
・意見を聴き、労働者派遣を受けようとする期間を変更した場合は変更した期間
・意見内容
4.派遣受け入れ期間の制限への抵触に関する通知義務
派遣期間制限の違反を防ぐため、派遣先、派遣元の間で抵触日に関する通知が定められております。2004年の労働者派遣法の改正で、派遣元から派遣先、派遣労働者にも通知する事が定められました。
- 派遣開始前
派遣先から派遣元へ派遣受け入れ期間制限への抵触日を通知します - 派遣契約締結時
派遣先から派遣元へ派遣受け入れ期間制限への抵触日を通知します。 - 派遣受け入れ期間制限抵触日の1ヶ月前から前日
派遣元から派遣先、派遣労働者へ派遣日以降の派遣を停止することを通知します。
5.派遣受け入れ期間に関して、良くあるお問い合わせ
請負業務で就業しているスタッフには就業先企業様から直接的指揮命令は出来ず改めて聴取する必要があります。
「反対意見」によって派遣受け入れができない事はありません。しかし、受け入れ反対に対する理由を確認し、見解解説や期間の再検討を行い、意見を尊重するように努める必要があります。
設定された考慮期間を過ぎても過半数代表者から意見が得られない場合は「意見なし」とみなされ、意見聴取の義務を果たしたことになります。
派遣期間制限に違反したことになり、雇用契約の申し込み義務が発生します。
抵触日に関する通知は書面もしくはFAX,Eメールなどで行います。